- HOME
- 学部・大学院・研究所
- 大学院
- 大学院工学研究科
- エネルギー化学専攻
エネルギー化学専攻 Chemistry and Energy Engineering
専攻の特色
エネルギー化学専攻は、次世代エネルギー社会の実現のために化学の視点から貢献できる技術者の育成を目的として、エネルギーに関連する物質や材料、デバイス、システムについての教育・研究を行なう、日本の他大学院では類例のない特色ある専攻である。低環境負荷で高効率なエネルギー利用技術の開発のためには、それを支える化学および化学と密接に関連した理工学分野の高度な専門知識と技術が必要とされる。このため、本専攻では以下の4学科目を設置し、機能性材料開発や燃料電池、太陽電池、光触媒、エネルギー変換デバイス、水素利用システムなどを主な対象として教育・研究に取り組んでいる。
-
エネルギー材料システム
水素エネルギーシステムの構築と高効率化、可視光型光触媒、酸化物イオン伝導体固体電 解質および電極触媒材料、燃料電池の性能向上と耐久性評価、高効率エネルギー資源変換、グリーンプロセス -
エネルギー材料評価
機能性材料の構造解析・特性評価、X線分析、化学反応解析、廃棄物回収・利用、水素製造、分子性材料、錯体化学 -
エネルギー材料化学
燃料電池用および色素増感太陽電池用構成材料、可視光応答型光触媒、有機分子組織体の機能性評価、新素材設計・合成・特性評価 -
高分子・バイオ化学
光重合反応、液晶化合物合成、抗菌性ポリマー、有機物質合成・変換、生体適合性微粒子材料
また、学問領域の垣根を越えた幅広い専門知識と俯瞰的視野をもつ研究者・技術者を育成するため、エネルギー化学専攻では電気電子工学専攻と共同で「先端ナノテクデバイス専修コース」を設置している。
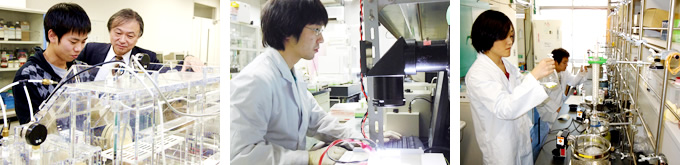
学習・教育目標と育成する人材目標
学習・教育目標
-
エネルギー化学分野における体系的かつ境界領域にまたがる横断的なカリキュラムの学習によって専門知識や技術・経験を習得させる。さらに「6.学科目の履修モデル」に示すとおり、自専攻科目以外にも工学研究基礎・教養科目を履修することにより幅広い基礎知識と語学力、工学の社会性、倫理観などの素養を身に付けるよう教育を行う。
-
学科目間で知識や技術を有機的に結合した教育を行う。
-
各自の研究テーマを推進することにより、幅広い基礎知識と最新の科学技術を学習させ、高い専門性を持つ技術者となる教育を行う。同時に、この過程においてコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を身に付けさせる教育を行う。
育成する人材目標
-
エネルギー化学分野の高度な知識と経験に基づく幅広い工学の専門的素養を備え、工学の社会性や影響力を理解し、課題解決能力とマネージメント能力に優れた人材を育成する。
-
創造性・独創性が豊かで、協調性と倫理観と共に高い行動力と広い視野を有する人材を育成する。
-
国際性を持った社会人としての基礎となるコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報技術力を備えた人材を育成する。
学位授与の方針
修士課程においては、以下のような素養を持った人材に対して修士(工学)の学位を授与する方針を持つ。
-
機能性素材の開発、エネルギー材料の分析と特性評価、エネルギーデバイスやシステムへの応用など、エネルギー利用を支える化学の基礎から応用までの幅広い領域をカバーするカリキュラムを確実に修得し、エネルギー化学分野に関する高度な知識と技術を身に付けている。
-
研究テーマ関連分野の理論・技術の研究・開発動向をグローバルな視点から常に注視し、学内外の院生・研究者と情報交換を行うことにより、課題発見能力や課題解決能力を身に付けている。
-
ティーチングアシスタント、インターンシップならびに大学や学会で企画される対外活動に積極的に参加し、専門職業人として社会の要請に応えられる能力、技術者としての広い視野と高い倫理観を身に付けている。
-
企業や他大学との研究交流、研究成果の学会発表、論文投稿など対外的な活動を積極的に行なって応用力と実践力を身に付けている。
-
英文での論文等の文書作成や国際的な会議での発表を通して語学力や国際性を身に付けている。
学科目 研究内容
エネルギー材料システム Energy Materials and Systems
環境対策を考慮した新たなエネルギー関連機能材料を開発し、これを包含するエネルギーシステムを構築して、その効率化を総合的に評価し得る人材を育成することを目標とする。材料を評価・分析するための手法・技術、材料を利用するためのデバイス化、デバイスを組込んだときの装置・システムとしての有効性評価と性能向上についての技術開発と教育を行っている。材料科学の知識・技術に加え、材料・デバイスを装置・システムに発展させるためのエネルギー工学についての専門知識・技術を学習・習得する。機能性材料としては固体酸化物形燃料電池や可視光型光触媒技術に対応する酸化物素イオン伝導体固体電解質・電極触媒材料、光触媒・改質触媒など、デバイスとしては圧電素子・熱電変換素子、燃料電池用電解質膜・セパレータなど、システムとしては固体高分子形燃料電池システムと固体酸化物形燃料電池システムの高性能化、低価格化および長寿命化を目指したセル構成、運転方法、システム構成などについて、広範囲な研究・教育を行っている。これらの研究テーマを通して材料科学とエネルギー工学に関する知識を吸収し、複合的・総合的な視点からエネルギー化学分野の諸問題をとらえることのできる能力を有する修士を育成する。
エネルギー材料評価 Energy Materials and Characterization
エネルギー材料分野で使用する新機能材料や化学反応プロセスの開発を目的として、環境負荷を考慮した発想・視点のもとに物質の調製や反応機構の解明と分析・解析による評価を行う。材料の組成・構造・組織をX線、電子線などを用いた計測・観察機器や各種分光装置、熱分析装置、クロマトグラフ等々により様々な観点から分析・評価し、また電気化学的特性、磁気的・光学的特性、表面・細孔特性などの計測により諸物性を明らかにし、機能材料の用途・応用を検討する。さらに酸化・還元、化合・分解、イオン交換などの化学的性質・反応の解明を通して、材料の化学的機能を創出する。具体的には、鉄廃棄物を用いた二酸化炭素の固定および水素製造に関する化学反応プロセスの検討、光触媒の形態制御と触媒活性の向上、重金属吸着性セラミックスの開発、さらには材料の分析・解析方法の改良や、新しい物理分析手法・装置の開発にも取り組む。種々の実験・評価・分析を通して計測・観察技術を習得すると共に、物質の化学的・物理的性質を総合的に評価する視野・判断力、材料開発における大局的な視点の育成を教育目標とし、材料特性評価や新材料開発および分析・計測技術の革新とその応用研究に携わる修士を育成する。
エネルギー材料化学 Energy Materials Chemistry
熱、電気、光、動力あるいは化学エネルギーなどの多様な形態をとるエネルギー間の相互変換、輸送、貯蔵および利用に関する技術は、必要とされる様々な機能性材料の探索、製法開発、機能改善によって支えられてきた。本学科目では環境に対する安全性・資源の継続性・リサイクル性などの社会的影響を考慮しながら、エネルギー関連の有機・無機機能性材料の改良・開発と分析・性能評価に関する知識と技術を習得する。特に、多岐にわたるセラミックスや有機材料あるいはそれらの複合材料の中で、固体高分子型燃料電池・直接メタノール型燃料電池の電解質膜・電極触媒、色素増感型太陽電池の構成材料、可視光応答型光触媒について、ナノ加工技術・ナノ構造体作成技術・分子配向制御技術などによって機能の大幅な向上を目指した新素材の設計・製造および特性評価に関する研究ならびに教育を行う。これらの取り組みを通して、有機化学・無機化学・応用化学の基礎知識とエネルギー関連材料に関する専門知識、機能性材料の製造・評価技術を学習・習得し、エネルギー化学分野で活躍できる技術者・研究者としての修士を育成する。
高分子・バイオ化学 Polymer Chemistry and Biochemistry
高分子化学とバイオ化学に関する教育・研究を通して、環境エネルギー材料分野における新技術・新材料の研究開発に従事できる優れた人材の育成を目指す。高分子化学においては高分子合成化学、機能材料化学、液晶化学、光化学を学習し、その基礎に立って新規な重合反応・素反応開発から化合物合成、物性・構造評価、さらに新物質やナノ構造に起因する機能材料開拓までを行い、実験技術・評価技術を習得する。素材としては容易に入手可能な化合物を利用し、化学技術により付加価値のある物質を創生することを目指す。具体的には、新しい導電性ポリマーの開発と蓄電デバイスへの応用、液晶を由来とするナノ構造材料の開発と発電デバイスへの応用、刺激応答型ポリマー電解質の開発と環境・エネルギー材料への応用などの研究テーマを通して高分子化学の基礎と応用を学習・習得する。バイオ化学においては生化学、生物反応速度論、生体触媒化学、バイオマス変換技術などを学習し、これらを基礎として、生体分子集合体を利用した新規機能材料の開発、酵素反応による有用物質の合成・変換技術の開発、生体高分子を基盤とする生体・環境適合性微粒子材料の開発、および各種エネルギー材料への応用など、多面的な実験・研究・開発を通してバイオ化学の種々の実験技術、評価技術の基礎から応用までを学習・習得する。以上のテーマに関する教育・研究を通して、この分野で活躍できる技術者・研究者としての修士を育成する。
進路/職業
修士課程修了学生は、習得した高度な専門知識と技術を生かし、電気機器、電子部品、自動車、化学材料および情報通信機器などのメーカーや、商社、ソフト開発会社、独立法人研究機関、各種研究機関など幅広い分野の企業や研究所に入社し、社会の第一線で活躍している。高等学校の理科および工業の専修免許取得も可能で、教員としての能力向上をはかって教職に進む道も開けている。修了した学生の一部は専攻の博士後期課程に進学し、さらに専門性を深めて研究を継続している。

